将棋世界1997年10月号、先崎学六段(当時)の連載エッセイ「先崎学の気楽にいこう」より。
竜王戦で、ついに近藤君が負けた。松本、行方と、得意のいい加減な中飛車(これは褒め言葉である)で連破したところまでは良かったが、佐藤康光君には通用しなかった。まわしをガッチリ引かれて押さえ込まれ、途中からは大差だった。近藤君は、最後、かけられるだけの王手をかけて、刀折れ矢尽き、玉砕した。
その数日後、将棋会館へ行くと、近藤君が事務所でニコニコしている。日焼けした顔にピンクのポロシャツなんか着ちゃって、早くも遊び人の雰囲気が漂っている。
「おう近藤君じゃないか、なんだい元気そうじゃないか、俺はてっきり打ちひしがれて憮然としているかと思ったよ」
背中をポーンと叩いていうと、近藤君は、相変わらずの脳天気な口調で喋り出した。
「いやあ先崎さん、序盤では勝てるかなと思ったすけど、本気を出されたっす。新潟の柏崎高校が甲子園でPL学園と闘ったようなものですよ」
「へっ柏崎高校?」
「僕は柏崎出身なんすよ。冬は雪が深くて練習ができないんです。見たこともない140kmのストレートでビビッちゃうんですよね。こちらは盗塁とか足で必死にかきまわそうとするけど、相手はホームランでカッキーン」
言うやいなや、本当にバットを持つかまえをしてくるんと回ってみせた。
「最後ね、代打攻勢をかけたっすよね。最後の夏、って思って思いきり振ったらなんとピッチャーゴロっすよ。しょうがないから、一塁にエイッと頭から滑り込んだっすよ。アウト!試合終了」
今度は頭から滑り込む真似をした。どこまでも脳天気な奴だ。
「涙が出たっすよね。仕方ないから甲子園の砂のかわりに特別対局室の空気をいっぱい吸って帰りました」
負けはしたものの、新四段で、あそこまで勝ったのだから大したものである。なんでも天から金がふってくるようだと、どこかでいったそうだが、ついこの間まで、無給の奨励会員だったのだから、素直な感想だろう。
「財布を開けたら諭吉さんがいっぱいあるっすよ。ついこないだまでは青い札だけだったのに夢みたいです」
こういう姿を見ると、やっぱり棋士は浮草稼業だと思う。一番勝つか、負けるかで、ガクンと収入も異なるわけである。自然に、お金に対する感覚もおかしくなっていく。
昔、20歳ぐらいの時に付き合っていた彼女は働き者で、2つのバイトをかけ持ちして、週に6日働いていた。時給は700円ちょっと、1日働いて5、6千円である。
ある時、僕がちょっと仕事をして、彼女の2週間分の収入を得たことがあった。いや驚いたのなんのって。
「でいくら貰ったの?」
「10万円」
「で何時間くらい仕事したの?」
「3時間」
「なにそれ……」
さらに彼女が呆れたのが、僕が、そうして得た金を、競輪で、1日で全部すってしまったことだった。
「こないだも半日で5万円の仕事をしたっていったわね。じゃあ、あれも―」
「あれ?あれはその日に飲んじゃった。パーッとね」
僕はその時の彼女の表情を今でも覚えている。口は半開きでパクパクし、目はうつろ。やっと出た言葉は「貴方は狂ってる」だった。
今にして思えば、純粋で、いい女の子だった。後日、お金の有難味について、こんこんと説教されたのである。
結局、しばらくして別れてしまったのであるが、彼女の言葉の中で一番印象に残っているのは「貴方を見ていると勤勉という言葉は罪悪だと思えてくる」だった。
(以下略)
——–
この時の近藤正和四段(当時)は、竜王戦決勝トーナメントで2勝し、3戦目(位置的には準決勝に進む一歩手前)で佐藤康光八段(当時)に敗れている。
先崎学六段(当時)は準決勝で、挑戦者となることになる真田圭一五段(当時)に苦杯を喫している。
——–
近藤四段の高校野球での例えが絶妙だ。
「最後ね、代打攻勢をかけたっすよね。最後の夏、って思って思いきり振ったらなんとピッチャーゴロっすよ。しょうがないから、一塁にエイッと頭から滑り込んだっすよ。アウト!試合終了」
なかなか熱血スポーツ根性ドラマのような展開にはならない。
本当に思いがこもった言葉だと思う。
——–
先崎学九段が20歳の頃に交際していた女性との話。
「貴方を見ていると勤勉という言葉は罪悪だと思えてくる」という言葉が発せられた段階で、黄信号あるいは赤信号が灯っていたと考えられる。
お互いが理解しあうことは難しいケースもある。
なかなか、当時流行っていたトレンディドラマのような展開にはならないのが現実の世界だ。
 どんどん強くなる やさしいこども将棋入門
どんどん強くなる やさしいこども将棋入門
 決断力 (角川oneテーマ21)
決断力 (角川oneテーマ21)
 羽生善治のみるみる強くなる将棋 序盤の指し方 入門 (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)
羽生善治のみるみる強くなる将棋 序盤の指し方 入門 (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)
![将棋世界 2015年10月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/615nQjVo3TL._SL160_.jpg) 将棋世界 2015年10月号 [雑誌]
将棋世界 2015年10月号 [雑誌]
 四間飛車を指しこなす本〈1〉 (最強将棋塾)
四間飛車を指しこなす本〈1〉 (最強将棋塾)
 羽生善治のみるみる強くなる将棋入門-5ヵ条で勝ち方がわかる (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)
羽生善治のみるみる強くなる将棋入門-5ヵ条で勝ち方がわかる (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)
 適応力 (扶桑社文庫)
適応力 (扶桑社文庫)
 ハンディー版 スグわかる!まんが将棋入門―ルールと戦法完全マスター
ハンディー版 スグわかる!まんが将棋入門―ルールと戦法完全マスター
 マンガ版 将棋入門
マンガ版 将棋入門
 大局観 自分と闘って負けない心 (角川oneテーマ21)
大局観 自分と闘って負けない心 (角川oneテーマ21)
 角交換四間飛車を指しこなす本 (最強将棋21)
角交換四間飛車を指しこなす本 (最強将棋21)
 プロの定跡最前線 飯島流相掛かり引き角戦法(将棋世界2015年10月号付録)
プロの定跡最前線 飯島流相掛かり引き角戦法(将棋世界2015年10月号付録)
 1手詰ハンドブック
1手詰ハンドブック
 寄せの手筋200 (最強将棋レクチャーブックス)
寄せの手筋200 (最強将棋レクチャーブックス)
 羽生善治のみるみる強くなる将棋 終盤の勝ち方 入門 (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)
羽生善治のみるみる強くなる将棋 終盤の勝ち方 入門 (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)
 3手詰ハンドブック
3手詰ハンドブック
 羽生善治のやさしいこども将棋入門-勝つコツがわかる5つのテクニック (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)
羽生善治のやさしいこども将棋入門-勝つコツがわかる5つのテクニック (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)
 捨てる力 (PHP文庫)
捨てる力 (PHP文庫)
 初段 常識の手筋(将棋世界2015年04月号付録)
初段 常識の手筋(将棋世界2015年04月号付録)
 プロの定跡最前線 矢倉△4五歩作戦の研究(将棋世界2015年09月号付録)
プロの定跡最前線 矢倉△4五歩作戦の研究(将棋世界2015年09月号付録)
 終盤が強くなる 1手・3手必至 (マイナビ将棋文庫)
終盤が強くなる 1手・3手必至 (マイナビ将棋文庫)
 透明の棋士 (コーヒーと一冊)
透明の棋士 (コーヒーと一冊)
 研究で勝つ! 相横歩取りのすべて
研究で勝つ! 相横歩取りのすべて
 羽生善治のこども将棋 中盤の戦い方 入門-駒を得して有利に進めよう! (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)
羽生善治のこども将棋 中盤の戦い方 入門-駒を得して有利に進めよう! (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)
 美濃崩し200 (最強将棋レクチャーブックス)
美濃崩し200 (最強将棋レクチャーブックス)
 四間飛車を指しこなす本〈2〉 (最強将棋塾)
四間飛車を指しこなす本〈2〉 (最強将棋塾)
 木村一基の初級者でもわかる受けの基本 (NHK将棋シリーズ )
木村一基の初級者でもわかる受けの基本 (NHK将棋シリーズ )
 上達するヒント (最強将棋レクチャーブックス(3))
上達するヒント (最強将棋レクチャーブックス(3))
 中飛車の基本 ゴキゲン中飛車編 (最強将棋21)
中飛車の基本 ゴキゲン中飛車編 (最強将棋21)
 石田流の基本―本組みと7七角型 (最強将棋21)
石田流の基本―本組みと7七角型 (最強将棋21)
 羽生善治全局集 ~七冠達成まで~
羽生善治全局集 ~七冠達成まで~
 羽生善治の将棋入門 ジュニア版
羽生善治の将棋入門 ジュニア版
 読みを鍛える7手詰200問 (将棋連盟文庫)
読みを鍛える7手詰200問 (将棋連盟文庫)
 早分かり 角換わり定跡ガイド (マイナビ将棋BOOKS)
早分かり 角換わり定跡ガイド (マイナビ将棋BOOKS)
 将棋教室 (マンガでマスター)
将棋教室 (マンガでマスター)
 復讐ゲーム ―リアル人間将棋― (メディアワークス文庫)
復讐ゲーム ―リアル人間将棋― (メディアワークス文庫)
 りゅうおうのおしごと! (GA文庫)
りゅうおうのおしごと! (GA文庫)




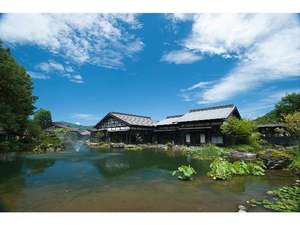










 鈴木大介の振り飛車のススメ (NHK将棋シリーズ )
鈴木大介の振り飛車のススメ (NHK将棋シリーズ )
 羽生善治のこども将棋 序盤の指し方 入門-1手目からの指し方と戦法を覚えよう! (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)
羽生善治のこども将棋 序盤の指し方 入門-1手目からの指し方と戦法を覚えよう! (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)
 聖の青春 (講談社文庫)
聖の青春 (講談社文庫)
 将棋連盟文庫 羽生の法則1 歩・金銀の手筋
将棋連盟文庫 羽生の法則1 歩・金銀の手筋
 逃れ将棋2
逃れ将棋2
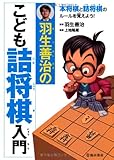 羽生善治のこども詰め将棋入門
羽生善治のこども詰め将棋入門
 直感力 (PHP新書)
直感力 (PHP新書)
 四間飛車を指しこなす本〈3〉 (最強将棋塾)
四間飛車を指しこなす本〈3〉 (最強将棋塾)
 どんどん力がつく こども将棋 強くなる指し方入門
どんどん力がつく こども将棋 強くなる指し方入門














